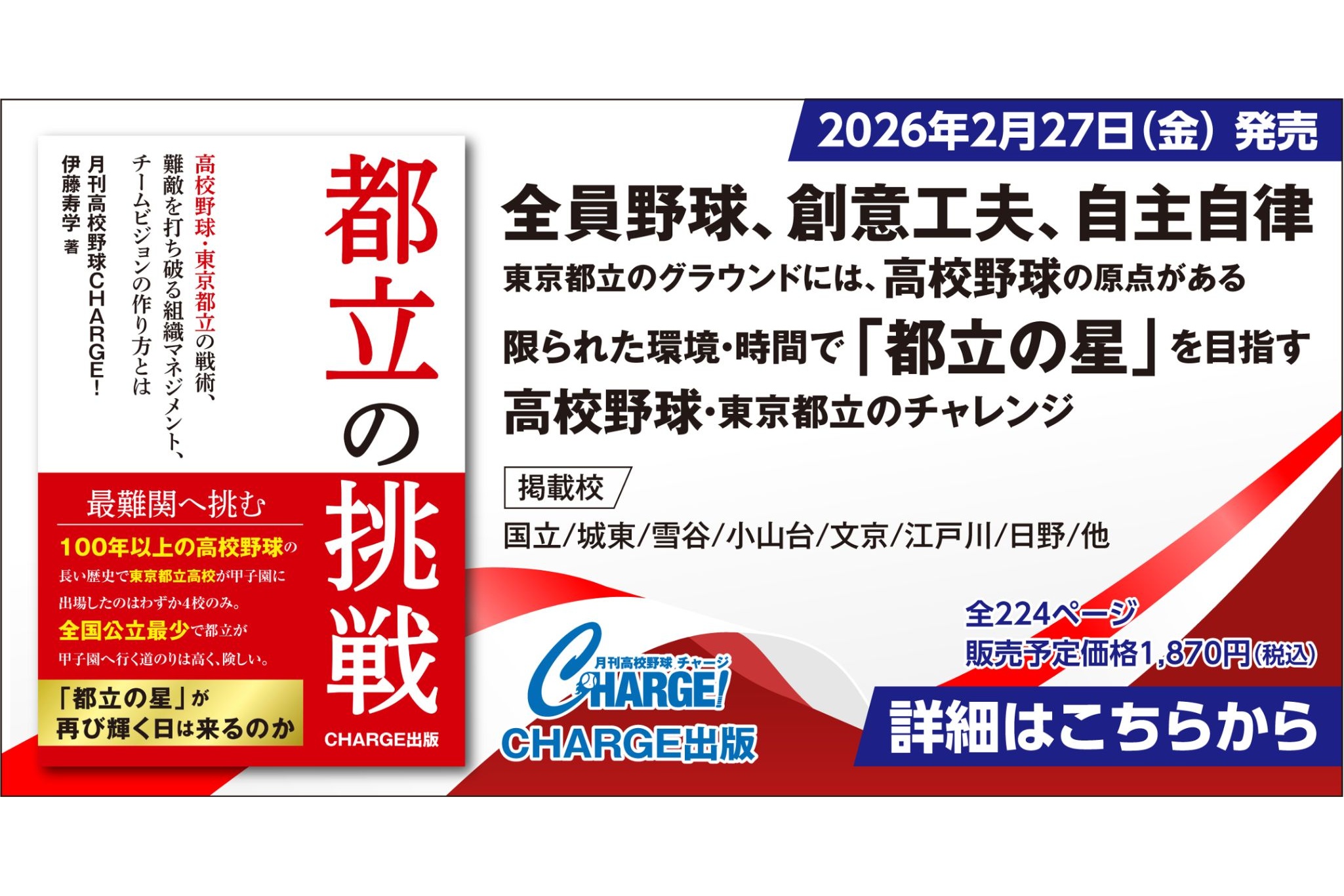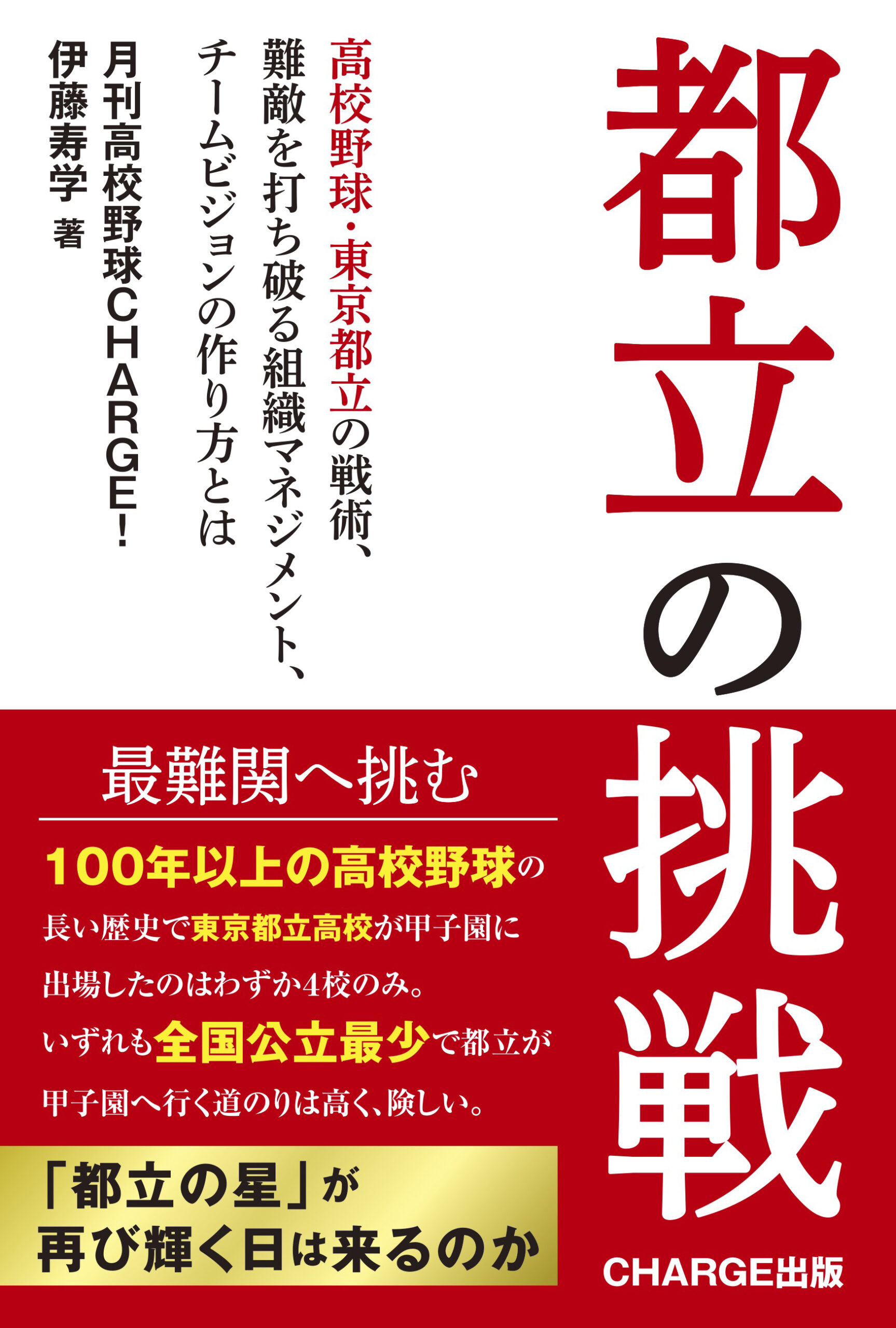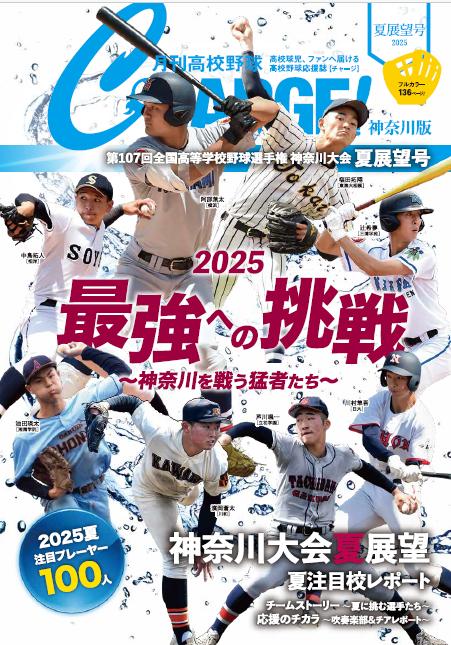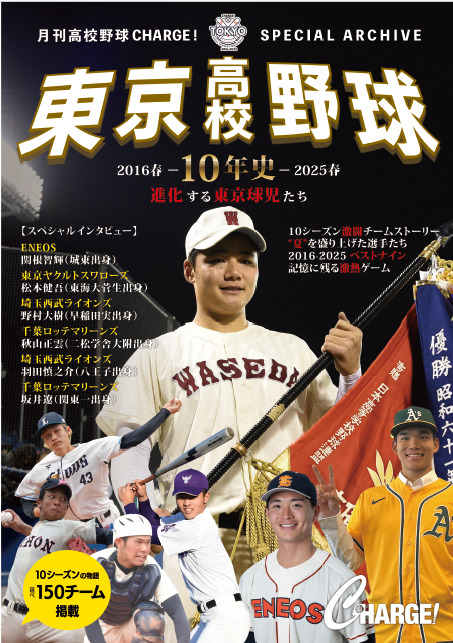栃木県下随一の伝統進学校の挑戦
大学野球観戦、企業訪問で社会力養成
栃木県下随一の伝統進学校・宇都宮は1924年夏に甲子園に出場した実績を持つ。伝統を継承する選手たちは101年ぶりの甲子園出場を目標に、心技体を磨いていく。
■OBの大学3年中山が東大で活躍
昨年度、東大合格者21人を記録した伝統進学校・宇都宮。野球部からも東大へ進み野球部でプレーする選手たちが増えている。宇都宮出身の東大3年中山太陽は、昨秋東京六大学リーグでの活躍が認められて外野手部門で初のベストナインを受賞した。1年生・荒井慶斗も宇都宮出身だ。宇都宮の現役選手たちは、昨秋の東大最終戦・対立教大を神宮球場で観戦。東大ベンチ裏スタンドに座り、先輩・中山をはじめ大学生たちの一挙手一投足に目を光らせた。木滝琉雅(2年=投手)は「中山先輩のプレーのほか、大学生ピッチャーのフォームや変化球のキレをみて迫力を感じた」と刺激を受けた。中山は年末の校内合宿に顔を出し後輩たちを指導、大学野球の魅力などを伝えていったという。先輩たちの好意によって、宇都宮の伝統がつながっていく。
■「瀧の原主義」が行動規範
学校では首都圏研修と題して、OBが働く企業などを訪問し社会を学ぶ。保科清樹郎主将(2年=外野手)は、金融関係の企業を訪ねて学部選択や将来へのヒントをもらった。「六大学野球や企業訪問での多くの学びを高校野球につなげていきたい」と話す。宇都宮は、1907年当時の学校長・笹川臨風の言葉「瀧の原主義」を校訓としている。「瀧の原主義は人物を作らんとするにあり~」と人間形成を追求する。宇都宮野球部は、この言葉を行動規範としてベンチに掲げている。篠崎淳監督は「先輩たちの活躍は、選手たちにとって一番の教科書。困難に向かって果敢にチャレンジしていく先輩たちの“生き様”が、野球、勉強において現役選手たちの力になっていく」と語る。
■101年ぶりの甲子園を目指す
チームの軸は俊足巧打のセンター保科主将、ピッチャーとレフトでプレーする木滝のほか、投打のセンスが光るエース見目脩介(2年=投手)たち。井戸沼耀太(2年=内野手)、北村駿磨(2年=捕手)も攻守の役割を果たす。秋大会以降は1年生も力を伸ばしチームの底上げが進む。保科主将は「1・2年生が学年の枠を越えて切磋琢磨していて全員でのレギュラー争いとなっている。守備からリズムを作って、粘り強く戦っていく」と春を待つ。宇都宮(宇都宮中時代)は甲子園での初開催となった1924年(大正14年)の第10回大会に出場し、栃木県初勝利を挙げている。目指すは101年ぶりの甲子園。難関に挑戦していくことが宇都宮の矜持だ。