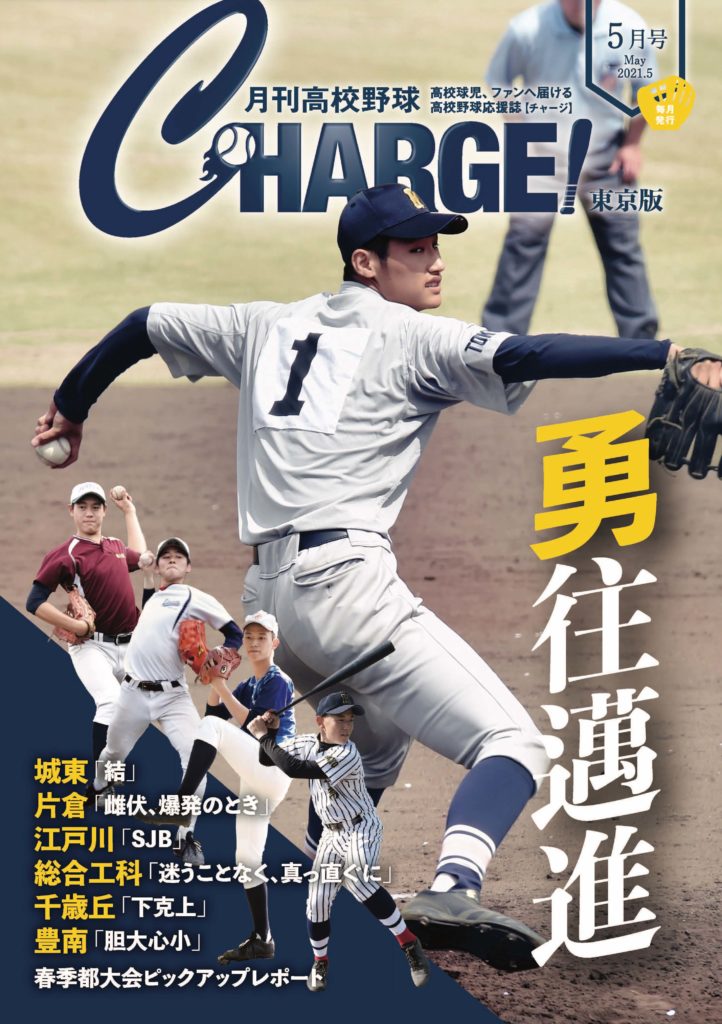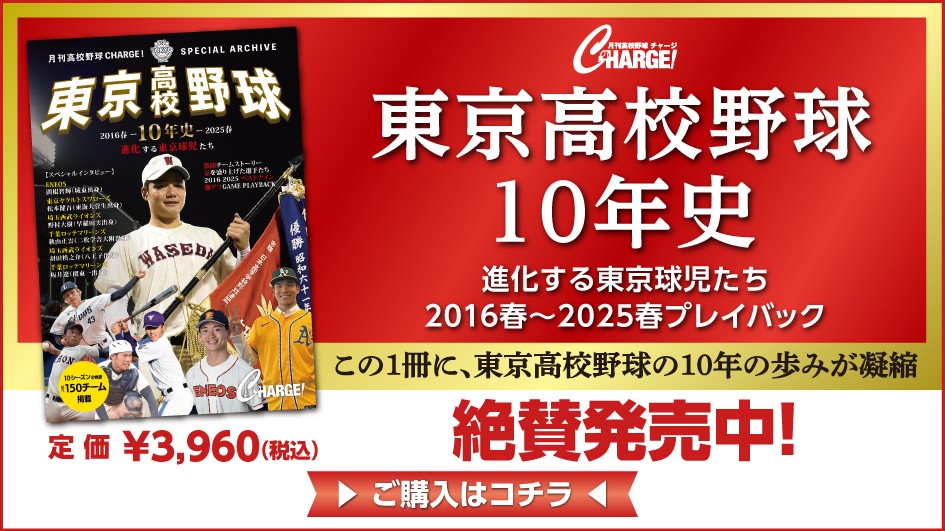【高校球児story】母に捧げる「最後の夏」
岩崎壮多(藤沢西2年=投手)
一番近くの応援団
藤沢西の左腕・岩崎壮多(2年)。
130キロ弱のストレートとキレのある変化球を駆使して、相手打者に立ち向かっていく強気なエースだ。壮多には、投げなくてはいけない理由がある。
野球を始めたのは小学校1年生のとき。いつも母が車で送迎をしてくれた。母はチームのスコアラーで、壮多にとっては一番近くの応援団だった。
試合の帰りは、車内での“反省会”が日課だった。スコアをつけていた母は、ピッチング内容をすべて把握していた。
「どうしてストライクが入らないの?」
「どうして強気のピッチングをしないの?」
母の質問は常に的を射ていた。だから、反省会が嫌いだった。負けた試合のあとは、黙り込んだ。内心は「野球をやったことないのに、うぜぇなぁ」と思った。
中学生になっても野球生活は続いた。いくつかのチームから誘いがあった中で、自分自身が成長できる場として藤沢西を選んだ。母は、目を細めて喜んでくれた。
悲しみの別れ
藤沢西での最初の夏、壮多は応援団長となった。ギラギラとした陽射しが照りつける中、スタンドで声をからした。母はその姿をじっとみていた。
母が入院したのは1年生の秋だった。専門医がいる大阪の病院で手術を受けた。父と兄が看病を続けた。「壮多は、野球を頑張りなさい」。母は、いつもそう言ってくれていた。その後、一旦は病状が安定したが、11月に再び悪化。11月末、神奈川の病院に転院した。
学校が終わると、毎日、病院に向かった。壮多は、三宅裕太監督の許可をもらい、練習を休んで母に寄り添った。幸せな時間だった。
1月上旬、母は、そっと目を閉じた。
ホームランボールを母へ
野球をやめようと思った。野球場には、いつも母がいた。でも、もういない。
グラブを見ると、母を思い出した。
「思い出すのがつらいので、もう野球はできません」。
三宅監督、森山渓太部長に打ち明けた。
「野球ができるようになったら戻ってこい」。
監督、部長からの言葉に勇気付けられた。
そして2月、グラウンドに戻った。仲間たちは、これまでと同じように迎え入れてくれた。自分には居場所がある。そう感じた。
それ以来、同級生の小野朗路、今井良祐の母親が1週間交代で昼弁当を作ってくれている。退院して体調が戻るまで弁当を作ることを、壮多の母親と生前に約束していたという。藤沢西はこんな仲間のいるチームだ。
壮多は、2年の夏ベンチ入り。マウンドに立つことはなかったが、3回戦三浦学苑戦ではブルペンに入った。新チームでは背番号1を背負った。
不甲斐ないピッチングをしたときは、三宅監督から「こんな姿をお母さんに見せられるか」と愛のゲキを飛ばされた。そして「お前はオレが一生面倒をみる。安心して野球を続けろ」と励まされた。
昨秋大会後の練習試合では、初めてホームランを打った。選手、指導者、保護者、みんなが喜んでくれた。ホームランボールは、母の遺影の横に置いた。
今春、3年生になる壮多は、多くの思いを抱えながら最後の夏へ向かう。
「まずは自分を支えてくれている父、兄、そして監督、チームメイトに恩返しをしたい。今年の夏は、母と一緒にやってきた野球の終着点。母のためにも、今までやってきたことをすべて出しきりたい」
母に捧げる「最後の夏」。一球一打を、天国の母に届ける。